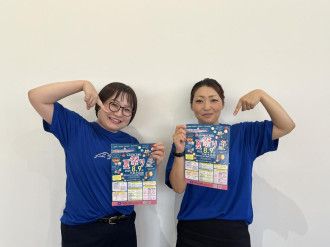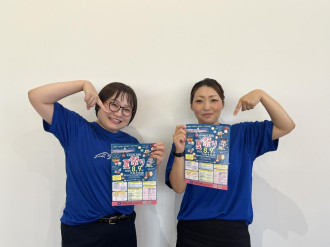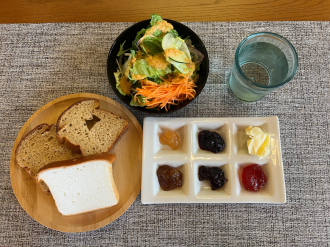学ぶ・知る
福智町市場で伝統の「初盆踊り」 江戸から続く口伝の儀式に100人

福智町市場の立花文麿さん宅で8月15日、初盆を迎えた故人を送る伝統の盆踊りが開かれ、地域住民ら約100人が集まった。
[広告]
この盆踊りは江戸時代に始まったと伝えられる。初盆を迎えた家々を巡るのが特徴で、今年は5軒を回った。コロナ禍による中断を経て、再開後、3回目となる。唄は、人生をテーマにした短い「端歌」と、物語を歌う長い「口説き歌」の2種類で、口伝で受け継がれてきた。
市場8区長の平川正貞さんは「かつては一軒に300人もの人が集まり、家の人がお茶や菓子を振る舞っていた。生演奏・生歌で行い、特に呼びかけなくても自然と人が集まるのがここのやり方。小さい頃から参加する中で歌と踊りを覚えていく」と話す。
東京から帰省中の幡野繭香さんは「個人宅でこれだけ集まるのは珍しい。自分が亡くなった後もこうして踊ってくれる人がいると思うと心の支えになる」と話す。12歳の長女の桃香さんは「小さい頃から10回以上参加している。みんなで踊れて楽しい」と笑顔を見せていた。
子どもの頃から参加しているという平川隆藏さんは「これが、お盆が来たと感じる合図。地元の伝統文化に触れさせたくて、子どもを練習から参加させている」と話す。踊りが開かれた家の遺族、今川脩平さんは「多くの方々に(昨年亡くした)祖父を送り出してもらえ、うれしい限り」と感謝の言葉を口にした。